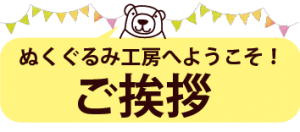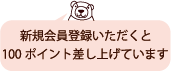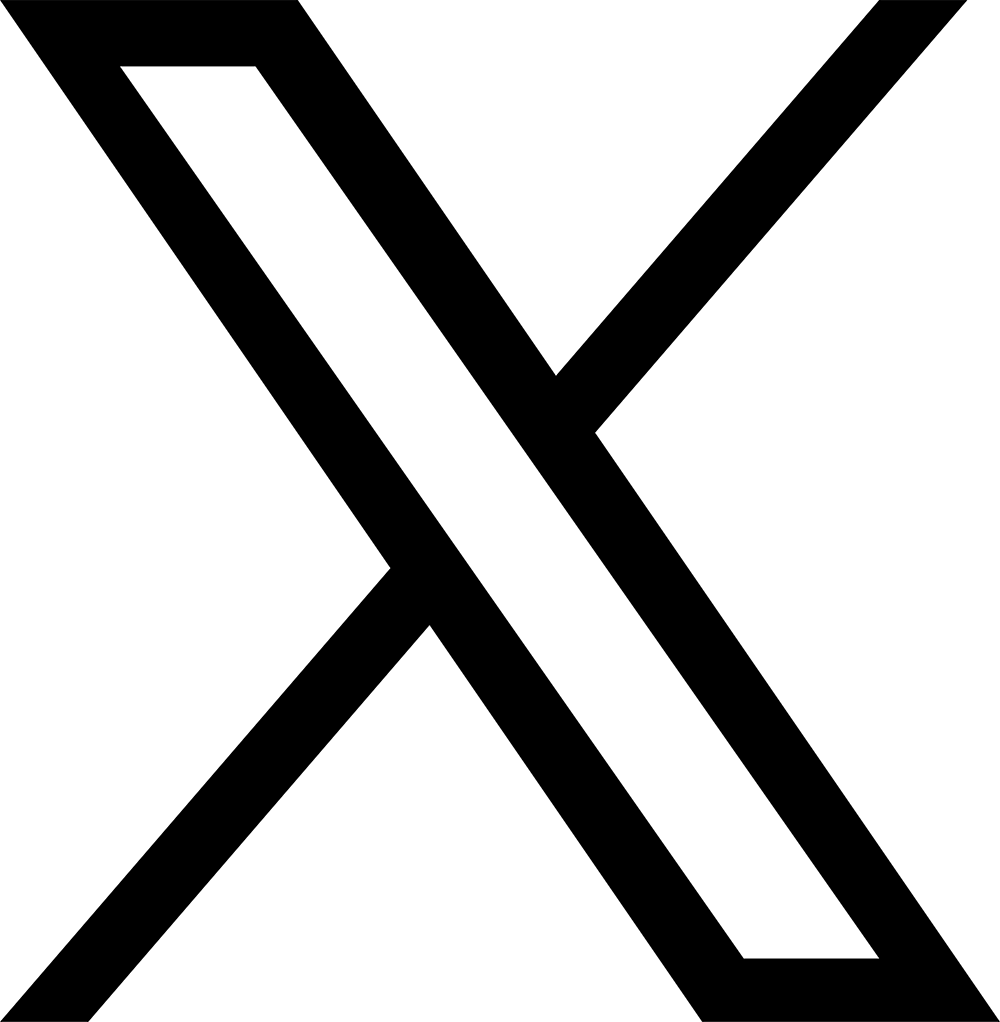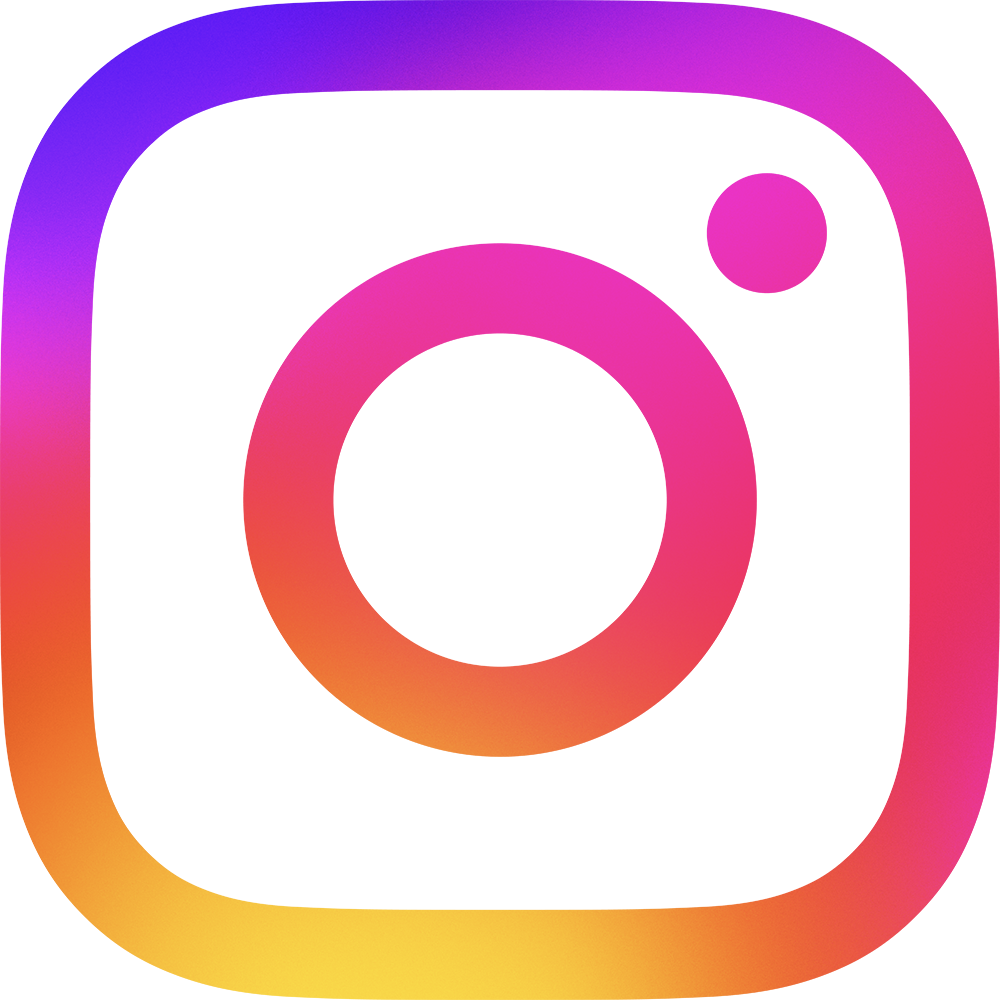こんにちは、天然素材のぬいぐるみ ぬくぐるみ工房です。
先日、現在国立科学博物館にて開催中の「古代DNA」展に行ってまいりました!
日本各地で発掘された古代の人々の骨に残るごく僅かなDNAを解読し、CG映像や資料などによって、
「日本人のきた道」を解説してくれる、壮大な企画展。
ヒトだけではなく、1万年前からの日本人の力強いパートナー、「イヌのきた道」もトピックとして解説してくれていまして、
なんとDNA分析をもとに復元した縄文時代と弥生時代のイヌの模型も初展示されると!
そう、その縄文犬と弥生犬の復元をどうしても早々に見たく急遽行ってまいりました。
【縄文時代のイヌ】猟犬としての役割
最古のイヌの系統はユーラシア大陸の東側のイヌのグループから約1万年前の縄文時代に日本列島に渡来し、
7000年間他のイヌと混ざらず系統を維持したそう。(イヌが日本列島に隔離されたため)
縄文犬の特徴
現代の柴犬程度の大きさで小型の猟犬だったと考えられている。
古代DNAから、この小型の猟犬が狩猟採集生活での食性に適応していたことが明らかになってきている。
縄文時代のイヌの頭骨を見ると、口吻が長めでストップが直線的であることがわかる。
また顔は細長くキツネ型の顔をしている。(キャプションより抜粋)
【弥生時代のイヌ】水田稲作文化のイヌ
弥生時代が始まり、ヒトの移動とともに異なる系統のイヌも渡来して在来のイヌと混ざりました。
弥生時代になると、稲作文化を伴ったヒトが日本列島に渡来、この渡来系弥生人が稲作文化の中で生きることに適したイヌを伴ってたそう。
そして稲作の広がりとともに、農耕文化の中で生きるイヌが、急速に在来の縄文犬に混ざりながら広がっていったことが古代DNAから明らかに。ヒトの文化の変遷がイヌのゲノムの変遷に直接つながっています。
弥生犬の特徴
縄文犬と比べて頭骨の大きさや形が異なる。
展示していた弥生犬2種はどちらも同じ遺跡から出土した頭骨から復元したもの。
一方は縄文時代のイヌの特徴を残しているがもう一方は口吻が短くストップが湾曲している。
また頭骨の幅が広く現代の日本犬に近いいわゆる丸顔のイヌである。
弥生時代になると日本人の食生活は狩猟採集型から農耕型に変わった。弥生時代に渡来したイヌは縄文時代のイヌと混ざりながら農耕社会におけるヒトからもらう食べ物に適応していった。(キャプションより抜粋)
ちなみに北海道の続縄文・オホーツク文化期には北海道北部沿岸部で海洋民族に飼育されており海産物の食物に適応していたそう。
頭骨は展示されていたけれど、こちらも復元してくれたら嬉しいなあ。
なお、展示しているイヌの骨のほとんどはDNA解析をしているそうです。
本当にすごいことです。
今回、打合せを終えて急遽向かったため、閉館までの時間は1時間のみ。
今回は縄文人と弥生人、縄文犬と弥生犬に焦点をしぼってじっくり見たため、
他にももう一つのトピックであるイエネコの歴史、それから古墳時代や琉球列島、アイヌ文化などがほぼ駆け足になってしまいました。
(時間的に遅かったせいか、科博の特別展にもかかわらず駆け足で見ることが出来たのはある意味良かったとも言えるかも)
6月15日(日)までの開催なので、4月6日の東京ハンドメイドマルシェが終わったら、また改めて行こうと思います。
今度は4時間くらいは時間をかけたい。とても楽しみです。
(ちなみに購入した図録には縄文犬や弥生犬の復元は載っていなかった。これは少しショック。
クマ形土製品やアイヌ文化のクマ製品も当たり前だけど図録は一方向からの写真のみなので、今度はもっとじっくり細かく見て来たい。クマ形は複製だけど底面も見られるように鏡があったので。)
東京ハンドメイドマルシェでは弥生犬のぬいぐるみに加え縄文犬のぬいぐるみをお披露目する予定です。お楽しみに♪





 横からのお顔のアップ
横からのお顔のアップ 左:弥生犬縄文型 右:弥生犬渡来型
左:弥生犬縄文型 右:弥生犬渡来型 横から。手前:弥生犬縄文型 後ろ:弥生犬渡来型
横から。手前:弥生犬縄文型 後ろ:弥生犬渡来型 弥生犬縄文型のみ横姿アップ撮影できた
弥生犬縄文型のみ横姿アップ撮影できた クマ形土製品 縄文晩期 2400年前 岩手県上杉遺跡 (複製)
クマ形土製品 縄文晩期 2400年前 岩手県上杉遺跡 (複製) クマ骨偶 8-9世紀 北海道トコロチャシ遺跡
クマ骨偶 8-9世紀 北海道トコロチャシ遺跡 イカ形土製品も可愛かったな 縄文後期 4000年前 北海道鷲ノ木4遺跡
イカ形土製品も可愛かったな 縄文後期 4000年前 北海道鷲ノ木4遺跡 製品カテゴリー
製品カテゴリー キーワード検索
キーワード検索