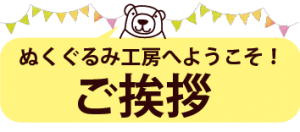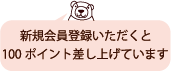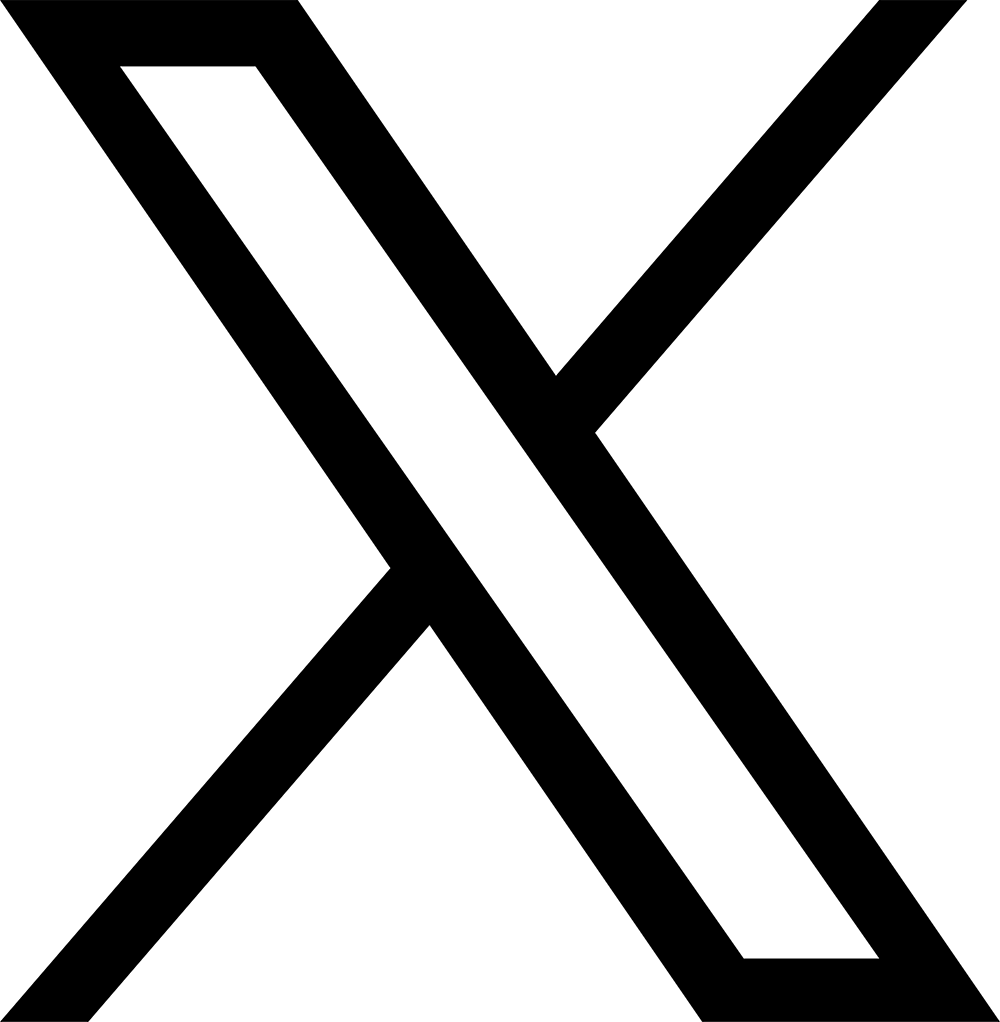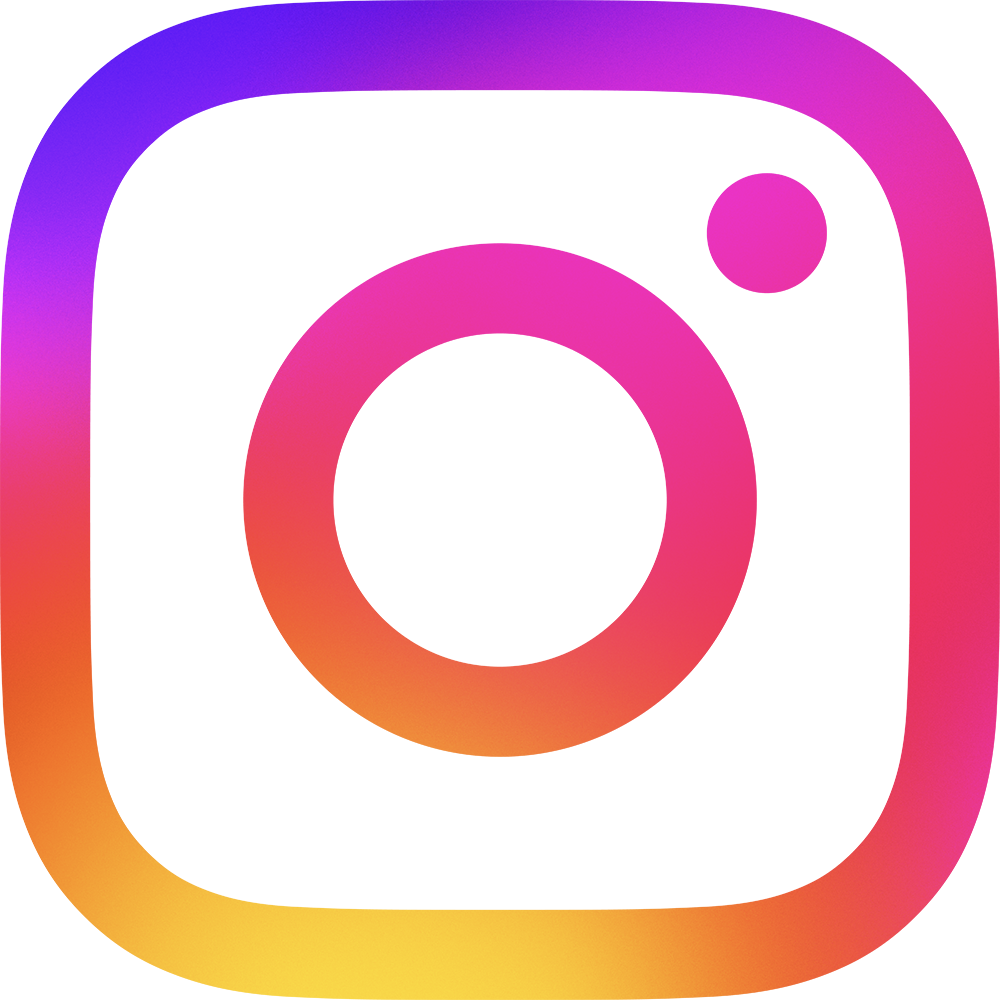こんにちは、天然素材のぬいぐるみ ぬくぐるみ工房です。
この度、ぬくぐるみ工房では「縄文犬のぬいぐるみ」と「弥生犬のぬいぐるみ」を4月6日のイベントにて販売開始いたしました。
2年前に出展した「弥生三人会」にて突如生まれた弥生犬のぬいぐるみ。この時はサンプルを開発したのみで販売までは出来ていませんでした。
それから早2年。お客様から弥生犬が欲しいとのありがたいお言葉をいただき、昨日出展した「東京ハンドメイドマルシェ2025春」にて無事販売開始することが出来ました。
弥生犬の隣にどうしても縄文犬も並べたくて、時間がかかってしまいましたことお詫び申し上げます。
イベント当日は、SNSを見ていらしてくださったかたが多く、本当に嬉しい一日でした。
今回本当はしっかり古代犬についてのPOPも作りたかったのですが、ぬいぐるみの制作時間でいっぱいになってしまい全く間に合わず。
そして初めましてのお客様も、縄文犬や弥生犬たちに目を留めてくださり、お客様との会話中に現代いる犬の種類かと思う方もたくさんいらしたので
それも踏まえて古代犬たちの特徴をまとめてみました。それから参考にした文献もまとめましたのでよろしければご覧くださいませ♪
縄文犬とは
1万年程前の縄文時代、南方から縄文人とともに日本列島にやってきたイヌ。7000年間、他のイヌと混ざることがなかった(島国で隔離されていた)。
縄文時代は狩猟採集の時代。縄文犬は人の狩りのパートナー、猟犬であった。亡くなってからも大切にされ埋葬された。
そのため全身骨格が各地で発掘されており250例ほどある。
体高は38cmくらい(35cm~43cm オスメスの性差が現在より大きくサイズにばらつきがある)、現在の柴犬くらいか少し小さいくらいか。
頭骨から見えてくる特徴は、ストップ(額から鼻筋にかけてのくぼみ。額段)が浅くほぼまっすぐ直線的。眉間の縦の溝も浅い。
顔幅は狭く口吻は長め。後頭部は低く、顔は細長くキツネ目。
猟犬だったからか四肢の骨が頑丈、足は短く、がっしりタイプである。
縄文犬の場合は立ち耳・差し尾、弥生時代に巻尾の犬が多くなったという説もあるようでこれをもとに
ぬくぐるみ工房の縄文犬のぬいぐるみは、立ち耳・差し尾とした。
骨からわかる特徴を出来る限りぬいぐるみの形状に再現しました。
弥生犬とは
2000年程前、大陸から渡来した弥生人とともにやってきた新しいタイプのイヌ。
大陸にはイヌを食べる文化があり、食用として解体され散乱して出土することが多い。
そのため埋葬された全身骨格が残る弥生犬は15例ほどである。
弥生時代も猟犬として活躍したことがわかる絵画が描かれた銅鐸が香川県で見つかっているので(伝香川県出土銅鐸)
猟犬としても人のそばにいたと思われるが役割を終えると最終的には食べられた模様。
だんだん縄文犬と交雑していったので形質は多様化。
大きさは体高47cmくらい。縄文犬より一回り大きい。
頭骨から見えてくる特徴は、ストップがやや深く(現代の柴犬よりは浅い)少し窪みがある。
顔幅は広く口吻は短い。後頭部も高く、顔は丸顔。
四肢は長いが筋肉の発達は弱く、いわゆる華奢なタイプである。
弥生時代には巻尾の犬が多くなったという説から
ぬくぐるみ工房の弥生犬のぬいぐるみは立ち耳・巻尾とした。
こちらも骨からわかる特徴を出来る限りぬいぐるみの形状に再現しました。
縄文犬と弥生犬の比較図です。
ぬいぐるみの素材はいつもと同じく、オーガニックコットン100%にこだわり、制作いたしました。
縄文犬の黒色部分は矢車附子で草木染め、弥生犬の茶色部分は天然の綿そのままの茶綿のお色です。
中綿もオーガニックコットン綿をしっかり入れました。
形状の関係でお洗濯はあまりお勧めしていませんのでご理解の程お願いいたします。
弥生犬と縄文犬が混じり合い、やがて地域ごとや飼う目的ごとに特徴を持った犬が作られていき様々な日本犬が生まれました。
なんと尊い存在。そんな2種類の古代犬を作ることが出来たことは本当に嬉しい限りです。
それも元は弥生三人会にお誘いいただき、弥生時代の素晴らしく可愛い弥生絵画の魅力を多々教えてくださった橋本桂子さんのおかげなのです。
橋本桂子さんは考古学を学ばれその仕事についた後、刺繍を学ばれ、草木染めを学ばれ、刺繍糸を自ら草木染めをして刺繍作品を作られています。(とにかくすごい人です!)
桂子さんの弥生絵画をモチーフにしたそれはそれは可愛い刺繍に出会ったときは思わず声が出たくらいで、本当に素敵な作品を作られています。
是非ウェブサイト「草木染de草花刺繍」をご覧ください。
なお、縄文犬・弥生犬を作るにあたり参考にした文献は以下の通りです。
各地の博物館に展示されている全身骨格・頭骨・キャプション・復元模型も合わせて参考にしました。
参考文献
内山幸子(2014)『犬の考古学』(ものが語る歴史30)同成社
河西健二(2023)「富山県小竹貝塚に埋葬された縄文犬」『milsil』第16巻第6号,9-12,国立科学博物館
小宮輝之(2021)『人と動物の日本史図鑑-1旧石器時代から弥生時代』少年写真新聞社
小宮孟(2021)『イヌと縄文人-狩猟の相棒、神へのイケニエ』吉川弘文館
谷口研語(2012)『犬の日本史-人間とともに歩んだ一万年の物語』吉川弘文館
林良博(2002)「ともに闘い、ともに生きた日本犬との絆、1万年」『週刊日本の天然記念物動物編』13号日本犬,16-17,小学館
山喜多佐和子編(2024)『日本の犬』誠文堂新光社
1996特別展『卑弥呼の動物ランド―よみがえった弥生犬』図録,大阪府立弥生文化博物館
2015特別展『海をみつめた縄文人-放生津潟とヒスイ海岸』図録,大阪府立弥生文化博物館
2024特別展『動物と考古学-愛でる、使う、食べる』図録,兵庫県立考古博物館
2025特別展『古代DNA∹日本人のきた道』図録,国立科学博物館
博物館
国立科学博物館 常設展及び2025特別展「古代DNA-日本人のきた道」
船橋市飛ノ台史跡公園博物館
大阪府立弥生文化博物館
兵庫県立考古博物館
最後に、他の新作時も同じくで恐れ入りますが、
これからまだ色を増やしたり(赤毛と黒毛をそれぞれ作るか、白い犬も作る?とか)形状を増やしたり(差し尾と巻尾もそれぞれいたのだからそれもそれぞれ作る?とか)する可能性もあるので、
しばらくは縄文犬・弥生犬ともにイベント出展時のみの販売とさせていただき、ある程度バリエーションが確定した時点でウェブサイトでも販売開始しようと思っています(時期未定)。
次のイベントは北海道札幌で開催のサッポロモノヴィレッジ2025春です。
その後のイベントについてはイベント情報をご覧ください。
それではまた、もりもりぬいぐるみ作りまーす!これからもよろしくお願いいたします。



 正面
正面 ななめ
ななめ 横
横 後ろ
後ろ 正面
正面 ななめ
ななめ 横
横 後ろ
後ろ


 イノシシを狩るイヌ
イノシシを狩るイヌ 製品カテゴリー
製品カテゴリー キーワード検索
キーワード検索